- シーンから探す
-
贈る相手から探す
- 彼氏
- 彼女
- 男友達
- 女友達
- 夫・旦那
- 妻・奥さん
- お父さん・父
- お母さん・母
- 両親
- おじいちゃん・祖父
- おばあちゃん・祖母
- 女性
- 男性・メンズ
- 妊婦
- 同僚
- 同僚(男)
- 同僚(女)
- 上司(男)
- 上司(女)
- 部下
- ビジネスパートナー・取引先
- 夫婦
- カップル
- 親友
- 女の子
- 子供
- 男の子
- 赤ちゃん・ベビー
- 乳幼児
- 1歳の誕生日プレゼント
- 2歳の誕生日プレゼント
- 3歳の誕生日プレゼント
- 4歳の誕生日プレゼント
- 5歳の誕生日プレゼント
- 6歳の誕生日プレゼント
- 7歳の誕生日プレゼント
- 8歳の誕生日プレゼント
- 9歳の誕生日プレゼント
- 10歳の誕生日プレゼント
- 18歳の誕生日プレゼント
- 19歳の誕生日プレゼント
- 20歳の誕生日プレゼント
- 21歳の誕生日プレゼント
- 22歳の誕生日プレゼント
- 25歳の誕生日プレゼント
- 26歳の誕生日プレゼント
- 30歳の誕生日プレゼント
- 40歳の誕生日プレゼント
- 50歳の誕生日プレゼント
- 60歳の誕生日プレゼント
- 70歳の誕生日プレゼント
- 80歳の誕生日プレゼント
- 88歳の誕生日プレゼント
- 90歳の誕生日プレゼント
-
カテゴリから探す
- 名入れギフト
- 記念品
- 文房具
- 花
- ビューティー
- こだわりグルメ
- ジュース・ドリンク
- お酒
- 絶品スイーツ
- ケーキ
- お菓子
- プリン
- フルーツギフト
- リラックスグッズ
- アロマグッズ
- コスメ
- デパコス
- インテリア
- キッチン・食器
- グラス
- 家電
- ファッション
- アクセサリー
- バッグ・ファッション小物
- ブランド腕時計(メンズ)
- ブランド腕時計(レディース)
- ベビーグッズ
- キッズ・マタニティ
- カタログギフト
- 体験ギフト
- 旅行・チケット
- ダレスグギフト
- ペット・ペットグッズ
- 面白い
- 大人向けのプレゼント
- 贅沢なプレゼント
- その他ギフト
- プレゼント交換
- 絆ギフト券プロジェクト
- リモート接待・5000円以下
- リモート接待・8000円以下
- リモート接待・10000円以下
- リモート接待・10000円以上
- おまとめ注文・法人のお客様
【中古】【茶器/茶道具 花入 掛置兼用】 一重切花入 銘「山路」 而妙斎宗匠書付 黒田正玄作 (掛置兼用花入・掛け置き兼用花入・掛け花入・掛花入・掛け用・掛用・置き花入・置花入・置き用・置用)
-
商品説明・詳細
-
送料・お届け
商品情報
残り 1 点 200640円
(2 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月15日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
-
ラッピング
対応決済方法
- クレジットカード
-

- コンビニ前払い決済
-

- 代金引換
- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
-
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)
-





























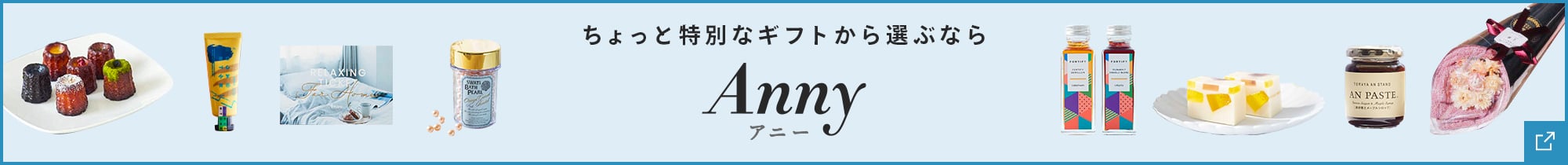




約直径天8.4cm
約高32cm
黒田正玄作
- 山路
- 旅のそま路。侘茶に相応しい銘(山路)
黒田正玄は千家の正統的な茶道具を制作する千家十職の一家(竹細工・柄杓師)です。「山路」は、俳句・詩・和歌など多くの例が思い浮かびます。
松尾芭蕉著「野ざらし紀行」に(山路来て何やらゆかし、すみれ草)があります。「熊野古道(世界遺産)など、多くの人が、古今の人の旅に、思いをはせます」
明治維新に至るまで将軍家御用柄杓師を務めました。
【初代 黒田正玄】
1578年天正06年~1653年承応02年
越前国黒田郡の出身で、名を七郎左衛門(後に正玄)、俗称を日参正玄といいます。
当地の丹羽長重に仕えますが、のち剃髪して「正玄」と改名し、近江国大津で竹細工を業としました。
天下一と称されていた一阿弥に師事したとされています。
後に上京して小堀遠州に茶の湯を学び、その推挙で将軍家御用柄杓師を務めました。
茶の習得に遠州に日参した為、「日参正玄」と呼ばれた。さらに、大徳寺156世江月宗玩に参禅した事でも知られています。
【2代 黒田正玄】
1626寛永03年~1687年貞享04年
初代 正玄の三男として生れ、名を宗正(後に正玄)といいます。
小堀遠州の推挙で3代将軍・徳川家光の御用柄杓師を務めました。
【3代 黒田正玄】1656年明暦02年~1717年享保02年
2代 正玄の長男として生れ、名を弥助(後に正玄)、号を正斎といいます。
5代 将軍・徳川綱吉の御用柄杓師
表千家 6代 覚々斎宗左、久田家3代徳誉斎宗全の御用を務めました。
1704年宝暦元年 長男・弥吉に家督を譲って隠居し、「正斎」と号す。
【4代 黒田正玄】千家職家となる
1692年元禄05年~1731享保16年
3代 正玄の長男として生れ、名を弥吉(後に正玄)といいます。
5代 徳川綱吉の御用柄杓師、表千家6代覚々斎宗左の御用を務めました。この代より千家職家となりました。
【5代 黒田正玄】1708(宝永5)年~1778(安永7)年
4代 正玄の養子で、名を才次郎(後に正玄)といいます。
8代 徳川綱吉の御用柄杓師、表千家7代如心斎宗左、裏千家8代一燈宗室、武者小路千家7代直斎宗守の御用を務めました。
【6代 黒田正玄】
1747年延享04年~1814年文化11年
5代 黒田正玄の次男として生まれ、幼名を正次郎、名を弥吉(後に正玄)、号を弄竹斎・玄同といいます。
10代 徳川家治の御用柄杓師、表千家8代そったく斎宗左、裏千家 9代 石翁宗室、武者小路千家 8代 休翁宗守の御用を務めました。
上京町年寄を務めました。
【7代 黒田正玄】
1768年明和5年~1819年文政02年
6代 黒田正玄の養子で、幼名を弥三郎、名を弥吉(後に正玄)といいます。
11代 徳川家斉の御用柄杓師、表千家 9代 了々斎宗左、裏千家10代認徳斎宗室、武者小路千家 9代 好々斎宗守の御用を務めました。
上京町年寄を務めました。
【8代 黒田正玄】
1809年文化06年~1869年明治02年
7代 黒田正玄の長男として生まれ、幼名を熊吉、名を弥吉(後に正玄)といいます
12代 徳川家慶の御用柄杓師を務めましたが、明治維新によって将軍家の庇護を失いました。
【9代 黒田正玄】
1837年天保08年~1859年安政06年
8代 黒田正玄の養子で、幼名を弥一郎、名を弥吉といいます。早世しました。
【10代 黒田正玄】1825(文政8)年~1900(明治33)年
8代 黒田正玄の婿養子で、名を利助(後に正玄)といいます。
9代 黒田正玄が早世した為、師・8代 黒田正玄の養子となって10代を継承しました。
1881年明治14年、長男・熊吉に家督を譲って隠居しました。
【11代 黒田正玄】
1869年明治02年~1911年明治44年
10代 正玄の長男として生まれ、名を熊吉(後に正玄)といいます。
表千家 11代 碌々斎宗左、裏千家 12代 又みょう斎宗室、武者小路千家 11代 一叟宗守の御用を務めました。
1881年明治14年 11代 黒田正玄を襲名しました。
【12代 黒田正玄】
1906年明治39年~1988年昭和63年
11代 正玄の長男として生まれ、名を久万吉(後に正玄)といいます。
父が逝去した時に未だ幼少であった為、黒田常次郎が後見となりました。
1926年大正15年 家督相続する。
1943年昭和18年 政府認定技術保存資格者
1976年昭和51年4月28日 紺綬褒章受賞。94歳で死去
【13代 黒田正玄 (本名 正春)】
1936年昭和11年生~
早稲田大学文学部卒
1966年昭和41年 13代を襲名
竹の花入
利休が伊豆韮山の竹で作ったのが始まり。
竹節を利用したり歪みやしみなど竹花入の見所です。尺八のような寸切・一重切・二重物など全体の姿・個性を
表現することが大切です。
竹は真竹の使用が多く、細工物に適しています。
籠花入
形の種類が多く歴代の御家元のお好や創造性のあるものが多く最も侘びた花入です。
籠花入には置籠が多く、他に手付・耳付・掛花入いろいろあります。
板床や畳の床に置く籠花入には薄板は使用しません。
花入の説明(敷板の説明)
花入の説明(敷板の説明)
掛物が一行物の時は床の下座(床柱のある方)に置くのが多い。
掛物が横軸の時は花入を中央に置くのが多い。
木地の薄板は水で濡らし拭ききって使用します。
関連商品